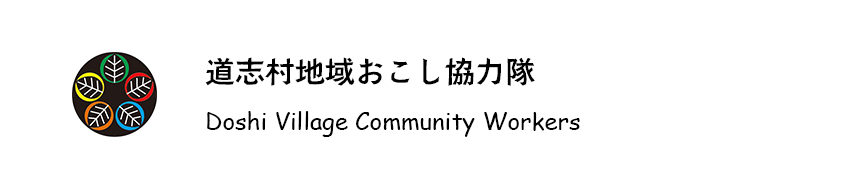祝 リトル・トリー設立
昨日、第一期協力隊の大野さんが設立した会社「リトル・トリー」の設立を祝う会が開催されました。
子供を含め30人くらい集まったでしょうか。
大野さんがネイティブアメリカン(インディアン)の少年の物語である小説「リトル・トリー」に出会ったのは高校生の時とのこと。大学院でネイティブインディアンの研究をして、実際に現地にも行っていたのですから、筋金入りです。
大野さんの道志村の生活第二ステージがいよいよ本格始動、私も負けておられんという思いです。
なお、妻は写真のようにお祝いのクッキーを焼きましたが、出かけようと準備をしている時に子供が顔を含め4か所をハチに刺されてしまい、あまりに痛がるので急きょ家族全員で富士吉田の病院に行きました。
お祝いの会には村に帰ってきて、私だけ2次会から参加させてもらいました。休日診療はどうしても村外になるので、改めて家族の健康管理について考えさせられました。
(千々輪)

水源の森の課外授業
SATOYAMA movementの取り組みとして道志村の水源林を学ぶ動画が配信されています!
モーニング娘。’16とハロプロ研究生の方に水源林の機能や間伐の必要性などを体験を通して学んでいただきました!
詳しくは以下の動画をご覧ください!

アイドルの方々の発信力は絶大!
たくさんの方に関心を持っていただけたのではないかと思います。
3月19日、20日には、これに関連して、パシフィコ横浜で「SATOYAMA&SATOUMIへ行こう2016」というイベントが開催されました。
道志に来てくださったモーニング娘。'16のみなさんと、こぶしファクトリーのみなさん、横浜市水道局水源林管理所 温井所長とステージに登壇し、動画の紹介とともに道志村の森づくりや鹿皮の利用についてお話をさせて頂きました。
イベントの参加者のかたへ抽選で贈られるプレゼントには、モーニング娘。'16の方にサインをして頂いた道志産鹿革のしおりを採用して頂きました。
また、ワークショップブースを出展させて頂き、みなもと体験館の木工体験や鹿革のブレスレットづくりの体験をおこない、多くのかたに道志の木や鹿革を手に取って頂くことが出来ました。
このような機会をいただけたことに感謝です!(香西)
川原畑のウラジロモミ
川原畑には県下で三番目の大きさを誇るウラジロモミがあります。
道志手帖10号の特集「人と木」で川原畑を代表する木として紹介しましたが、写真に撮ったのはスギの大木でした。ドウシテこんな間違えをしたかというと、現地にある看板の矢印の方向を見ると、ちょうど社殿の横方向に大木があり、てっきりそうだと思い込んでしまったでのす。葉や樹皮で違いが分からなかったのが恥ずかしいです。11号で間違いと訂正を掲載させてもらいました。
ウラジロモミは社殿を正面に見て斜め後ろにあります。真新しい祠がしたにあります。
近くからだと他の木がからんでいるので分りにくいのですが、ちょっと離れて生活改善センターの方から見ると大木というのが良くわかります。(千々輪)
【写真】 左:看板、 中:間違って紹介したスギの巨木(右端) 右:ウラジロモミの巨木
道志村は林業再生先進地?
北杜市のマクロビオテック講習会に不定期に参加しています。東京の講習会に行くよりもリラックスして受講できます。何度か北杜市を訪れ、この土地が都心から多くの移住者をひきつけていることが実感できました。
たまたま広報と議会だよりを読んだところ、議会だよりに地域おこし協力隊を活用した林業の再生について、先進地である道志村を参考にしたい旨が書かれていました。外から見ると、道志村は先進地だったんですね。(千々輪)


森林整備現場見学
山梨県民は平成24年度より一人年間500円の森林環境税を取られており、これは県の約77.8%を占める森林整備に役立てられています。
県主催でその環境税を活用した森林整備現場の見学会があり、勉強のため参加してきました。郡内と国中の2コースがあり、昨日開催の郡内コースに参加。25名の参加がありました。
山梨県の森林率は全国5位、うち44%が県有林という全国的にもまれな存在とのこと。県の森林環境部森林環境総務課の方の解説の受けながら都留市の間伐林の見学を行った後、間伐材を活用した炭製品や炭を肥料に使った野菜やその野菜を使ったジャラートを商品化している株式会社炭香に立ち寄り、その取組みを紹介して頂きました。写真右と中が見学の様子、左が炭香の商品の一つ炭の招き猫です。
また富士山科学研究所に行き、富士山ろくの森林について研究員の方から解説を受けました。
(千々輪)
子供たちと木を切る
拓哉君と一緒に子供たちの間伐体験に行ってきました。この日は8人中6人がのこぎりを使ったこともない子供たち。しかも小学校低学年が多く、だいぶ難しいな~と思っていました。
上の写真は林業のお兄さん、水越さんによる伐倒のレクチャーです。この後枝払いでのこぎりの練習をして、樹皮をはぎました。その後自分たちで受け口、追い口を作って伐倒。なんとか時間内にメニューをこなせました。最後に水越さんが自分たちが伐倒した木を各自好きな大きさに輪切りにしてくれお土産にしたのが好評でした。(千々輪)
都留文科大学間伐体験

4月から始まった都留文科大学の授業も今日で体験は最後です。今日は白井平地区の山で間伐とベルトスリングを使った搬出、玉切りをおこないました。
今回はノコギリでの伐倒後、木の皮をむいてみました。皮をきれいにむく作業は、木が水を吸い上げている今の時期にしかできません。切れ目をいれるとおもしろいようにきれいに皮がむけ、学生に好評でした。
むいた木の肌はすべらかで、さわるとぬれていて、木が水を吸っていることがわかります。
体験後は温泉にはいってもらいます。来週は大学で報告会、8月には有志でBBQを企画中です。(香西)
森の間伐&野草狩りツアーin道志村

6月29日(日)、横浜から10名強の参加者が道志村を訪れ、野草摘みと間伐体験をしました。
雨が心配でしたが、当日は晴れ間がひろがりました。
谷相地区で野草摘みのあと、鹿肉カレーとサラダ、野草のランチをつくって食べ、午後は間伐体験です。山では、三つ葉、たらの芽、フキ、わらび、桑の実、シオデ、サンショウ、セリなど、まだ食べられる野草がいっぱいありました。
鹿肉カレー、サラダの食材は、ほぼすべて道の駅で調達した道志産。おいしかったです。
午後の間伐は手ノコで20センチ級のスギを伐倒。雨にふられずに無事終了しました。(香西)
都留文科大学の学生が道志村に来ています
4月から、毎週金曜日に都留文科大学 環境・コミュニティ創造専攻の1年生が授業の一環で道志村に来ています。
20人×3グループがそれぞれ3回道志に来て、森林の現状や木の駅の取り組みについて学び、木材搬出や薪割りの体験をします。雨の日には協力隊の活動について話を聞いてもらいました。最終回には大学で学生によるまとめの報告会が予定されています。(香西)
境界確定作業

4月7日、境界確定をすすめるため大野さんと山へ行きました。森の手入れをするには、まず境界がわからないとできません。山に入り地図を確認しながら境界に沿って杭をうっていきました。山を歩いているととても気持ちがいいお天気です。林内には鹿のフンと、ヤシャブシの実がたくさん落ちていました。(香西)
シンポジウム 再生可能エネルギー事業の展開と課題 参加報告

2月23日(日)日本青年館でシンポジウムが行われました。
「農山漁村地域における地域住民主体の地域資源活用を考える
ー再生可能エネルギー事業の展開と課題ー」
というもので、協力隊 大野さんがパネリストの一人として報告をしました。
シンポジウム開催趣旨
http://jicr.roukyou.gr.jp/blog/archives/2014/0213_1404.php
プログラムは以下です。(チラシより)
第一部 基調講演「地域再生の実践ー農山村コミュニティの可能性を考えるー」小田切徳美さん
第二部 パネル報告
Ⅰ 「再生可能エネルギー地域自給圏の展望とFITの功罪」小林久さん
Ⅱ 「道志村における間伐材のエネルギー利用と新たな展開について」大野航輔さん
Ⅲ 「イタリアのコミュニティ協同組合とネットワークの力」田中夏子さん
Ⅳ 「再生可能エネルギー事業と住民参加ードイツのエネルギー協同組合を中心にー」
全体まとめとコーディネート 甲斐良治さん
香西が当日参加したメモを書いておきます(間違いがあったらご指摘ください)。
パネル報告後のパネルディスカッションでは、冒頭でまとめ
1 エネルギー自給は地域の誇りになる
2 担う組織体制に課題がある
3 利用者の共感を得ることが重要
その後、都市農村交流の重要性、その例として道志村と横浜市の関係、またドイツ・イタリアの共感・合意形成のありかたについてお話がありました。
また、大野さんから他のパネリストのかたへの質問として
1 住民との合意形成はどのようにしたらいいか
2 事業体としてどのような形態がいいか
これについて他のパネリストのかたが答えてくださいました。
1についての回答
・集落の既存の意思決定体制を変える必要があること
・「あなたがやるなら応援する」という関係づくり
・エネルギーそのものに関心を持つ世代はマイノリティであり、それ以外の関心に訴える必要があること(売電収益で地域でなにができるか、地域の困りごとの解決手段として)
・合意形成を促すコーディネート機関が必要(地域のことがよくわかり、一定の距離がある)
・地域のニーズを拾い上げること
2についての回答
・参加者に利益になる仕組みであること
・日本の法律は修正が必要であるが、当分は株式会社でも可ではないか(お金に応じない議決権を決めるなど)
・アイデンティティの醸成の場としてコミュニティ協同組合
・有限会社(お金を早く集められる)
(香西)
再生可能エネルギーに関するシンポジウム(2月23日開催)

大野さんが2月23日に日本青年館で開催される再生可能エネルギーに関するシンポジウムに参加し、道志村の間伐材のエネルギー利用についてパネル報告をすることになりました。
企業の森 木材搬出

12月7日、板橋地区の企業の森で森林体験活動をおこないました。
協力隊も木材の搬出のサポートをしました。
おもに林内作業車「マウントポニー」を使って集材作業です。
この機械は、華奢ですが、強いパワーでワイヤーをつかって丸太をひっぱることができます。
林内にはシカの角が落ちていました。シカの角は漢方薬にも使われるとか。
おもいがけないひろいものでした。
香西
「山梨県道志村の薪ボイラーと木の駅プロジェクト」について報告【12月3日(火)】
続いて投稿になりますが、BS11の放送と重なる形で(偶然ですが・・・)、薪ボイラーと木の駅プロジェクトに関する取り組みについて、バイオマス産業社会ネットワーク第131回研究会で報告をさせて頂く機会があります。
ご関心のある方は是非、ご参加頂ければ嬉しいです。
<バイオマス産業社会ネットワーク(BIN)第131回研究会のご案内>
日 時:2013年12月3日(火)18:30〜20:30
テーマ:「山梨県道志村の薪ボイラーと木の駅プロジェクト〜林業再生と地域活
性化を目指して〜」
講演者:大野航輔氏(道志村地域おこし協力隊、NPO法人道志・森づくりネット
ワーク)
会 場:地球環境パートナーシッププラザ
(東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学1F)
地下鉄表参道駅より徒歩5分・JR他渋谷駅より徒歩10分
参加費:BIN会員 無料、一般 1,000円
【お申込み】http://www.npobin.net/apply/
(大野)
道志・森づくりフェス

13、14日の二日間、イベントが行われました。
道志村の山林について考えよう!という趣旨でNPO道志・森づくりネットワークが主催した「道志・森づくりフェス」です。
木の駅どうし、森のコテージ、林間広場を会場に、間伐体験や木工展示等が行われました。
協力隊もそれぞれに関わりました。
大野さんは「ロケットストーブ」づくりのワークショップ、それにライブ。
井口さんはコーヒーの出店、千々輪さんは道志豚の豚汁販売の応援、中嶌くんはしょうゆ搾り機の展示です。
宣伝不足や内容の少なさ等、課題もありましたが、訪れたかたから「継続は力」との言葉もいただきました。どのように次につなげていくのかが大事です。

チッパー作業・わさび植え 2013/8/21
NPO道志・森づくりネットワークで、山にわさびを植えました。
整備したのは、谷相地区の山です。
間伐がされ、明るく気持ちのよい山です。林床には三つ葉やドクダミ、名前のわからない刺のある草が生えています。
スギの枝葉をどかし、細い丸太で杭を打ち囲いをつくったところへ、チッパーで枝葉をチップにし、敷き詰めます。
チッパー「スカット」は繊細で、なかなか作業がはかどりません。
振動も激しく、音もうるさいですが、枝をのみこんでゆくようすは愉快です。
植えたわさびは20株ほど。うまく根付いてくれるでしょうか。
今後の変化を見守っていきます。
香西

林内作業車、到着 2013/6/13
待ち望んだ林内作業車を、千葉県山武市で市民参画による木材集積所を展開する、NPO法人元気森守隊からお借りすることになりました。事務所がある花島産業さんのヤードへ行くと、多くの木材が堆積されており、嬉しくなります。前職、森のエネルギー研究所勤務時に、一緒に仕組みを作り上げて来てから約3年。山武市も積極的に事業を応援しており、今後の展開に期待したいです。
市内のサンブスギ林は溝腐病が蔓延しており、一刻も早く整備を行い、病気の進行に歯止めをかける必要があります。また、溝腐病のスギは歩留まりが悪く製材利用等、マテリアル利用が困難です。そのため、エネルギー利用による化石燃料代替と、民有林整備を同時に達成することが狙いです。大野


小菅村へ木材搬出の応援に 2013/4/11
小菅村地域おこし協力隊の関口くんから依頼があり、木材搬出の手伝いに行きました。協力隊としては赴任後、初の現場での恊働作業。中嶌くん、香西さんは都留文科大学の新卒。意を決して、道志を選んだ、本当に貴重な人材です。