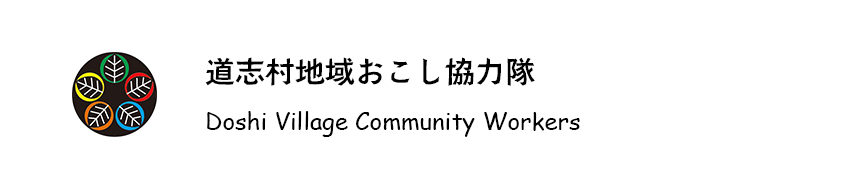山梨日日新聞でしょうゆプロジェクトが紹介されました

ご縁あって、2013,11/29付けの山梨日日新聞に掲載していただきました!
「しょうゆ搾り器」はなかなかなじみのないものだと思いますが、家庭用のしょうゆ搾りには欠かせない器具です。
シンプルな構造ながら、様々な工夫がつまった搾り器となっています!
なかじま
麻績村訪問2日目は・・・
前回までのあらすじ
道志村の協力隊のなかじまは「麻績村のしょうゆづくり」を見聞きしたいと思い、いざ長野県麻績村へ!
そこでは、来春しょうゆに仕込まれる大豆の脱穀作業とおいしいお茶の時間、そして現存するしょうゆづくりの施設が待っていた!
様々な刺激や感動のなか、しょうゆづくりへの想いはますます強くなっていった!!
というような内容となっています〜

前回ご紹介できなかった麻績村訪問2日目の様子です!
しょうゆづくりを訪ねて〜長野県麻績村へ〜
あれは10月のある日。
「長野県麻績(おみ)村の協力隊がしょうゆづくりをしている!」と聞きつけました。
道志村でしょうゆづくりをやろうとしている私にとっては興奮するような情報でした!
早速、麻績村地域おこし協力隊のホームページを拝見すると、かつて使われていたというしょうゆづくりの道具の数々が紹介されていました。
そして記事を読み進めていくと「地区の方々と来春にしょうゆを仕込む」との記述が!!!
これはぜひとも麻績村のしょうゆづくりについて聞きたい!体験したい!
そんな私の勝手なお願いを聞き入れていただき、今回の麻績村訪問が実現しました!!
【麻績村ポータルサイト おみも】
http://www.omimo.info/chiikiokoshi/cat3/post_5/ [醤油づくりを訪ねて]
http://www.omimo.info/chiikiokoshi/cat1/post_14/ [醤油プロジェクト始動!]
とっても興味深い記事です!!!
11/23,24と麻績村を訪問して見聞きし、体験したあれこれをご紹介します!
道志村から約200キロ。
長野市と松本市の中間あたりに麻績村はあります。
JR線と長野自動車道が通り、とてもアクセスしやすいところです。
山々に囲まれ、北アルプスが見守ってくれているような印象を持ちました!
1日目(23日)は麻績村の矢倉地区にて、しょうゆを仕込むために栽培された大豆の脱穀作業をするとのこと。
しょうゆづくりを知る村の方々との作業ということで、お手伝いと聞き取りをさせていただきました。
野原の麦畑

今日畑に行ってみると、麦が発芽していました。
先週中嶌君の麦畑はすでに発芽しているのに、標高が低い自分の畑は発芽していなかったので心配していましたが、無事発芽しました。
様子からして3日くらいたっているかなと思います。
11月6日、7日に種を撒いた分が発芽していたので、約3週間で発芽しました。
寒くなり朝早起きができないので、23日(土)以降は間近で見ていませんでした。畑は毎日見るべしと思いました。
一昔前までは麦が村内で栽培されていました。私が麦を植えたのも村のかつての姿を見たかったからです。
(千々輪)
「山梨県道志村の薪ボイラーと木の駅プロジェクト」について報告【12月3日(火)】
続いて投稿になりますが、BS11の放送と重なる形で(偶然ですが・・・)、薪ボイラーと木の駅プロジェクトに関する取り組みについて、バイオマス産業社会ネットワーク第131回研究会で報告をさせて頂く機会があります。
ご関心のある方は是非、ご参加頂ければ嬉しいです。
<バイオマス産業社会ネットワーク(BIN)第131回研究会のご案内>
日 時:2013年12月3日(火)18:30〜20:30
テーマ:「山梨県道志村の薪ボイラーと木の駅プロジェクト〜林業再生と地域活
性化を目指して〜」
講演者:大野航輔氏(道志村地域おこし協力隊、NPO法人道志・森づくりネット
ワーク)
会 場:地球環境パートナーシッププラザ
(東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学1F)
地下鉄表参道駅より徒歩5分・JR他渋谷駅より徒歩10分
参加費:BIN会員 無料、一般 1,000円
【お申込み】http://www.npobin.net/apply/
(大野)
BS11で協力隊の特集が放送【12月1日(日)】
来る12月1日(日)18時〜19時、BS11チャンネル「ウィークリーニュースONZE」で協力隊の特集が放送されます。【番組URL:http://www.bs11.jp/news/2143/】
週刊朝日の「あまちゃん特集」で、「地方に向う若者」として取り上げて頂いたことがきっかけとなりました。
今回は、特に林業や薪ボイラーの取り組みに関する内容がメインとなりますが、協力隊5人の活動のみならず、道志村役場の協力隊担当とみさん、薪の供給を担う方々や、山林所有者の方等に出演頂き、協力隊が行っている活動の全体像が伝わる内容となっています。
全国各地の協力隊と同様に、役場や村内外の、自分たちの取り組みに関心を持って下さる方々に支えられつつ、自分たちの活動が進んでいくことを実感しました。
今回、取材を行った方は、田中あき子Jerryさん【http://akikojerry.web.fc2.com】。
単身、カメラを片手に道志村へ来村。僕たちの取り組みを密着取材しつつ、全体構成を描きながら活動の一部一部をカメラに収めていく。その姿に、身が引き締まる思いでした。
そして、取材の当日に発覚した事実。どこかで会ったことがあるな・・・。あ!と。
自分が7年ほど前に踊りの活動をしていた頃、活動を供にした旧友でした。あだ名で呼んでいたのでわからなかった!
点が線となるとは、こんな瞬間でしょうか。
そんな偶然もあり、今回の取材には、個人的にも思い入れがあります。
私(大野)の取り組みもまだまだ発展途上。だけど、周囲に頼りになる方々がとても多いこともあり、楽しく、真剣に、活動しています。放送日当日は、生放送のため、自分もスタジオでコメントさせて頂く予定です。ご都合の合う方、是非ご覧下さい。(大野)
渋柿 柿渋

11月になると家々の軒先に柿が吊るされている光景が見られ、美しいです。
今日は季刊誌配布先のおうちで、道志の柿事情についてお話を聞くことができました。
また、柿渋染をされている人にもお会いしました。写真は、わかりにくいですが「うづくり」の杉板に柿渋を塗ったものです。柿渋を使ったものづくりのおもしろさをお聞きしました。こちらも奥が深いです。
季刊誌を配るために歩いていると、道志村にはいろいろな技を持った人が集まっているのを知ることができます。小さな村にこれだけいろいろな作家さんがいることは、村の魅力のひとつだと感じます。
香西
大栗の畑 秋

夏野菜の収穫以来何もせずにいた大栗の畑ですが、千々輪さんにいろいろ提案いただき、そら豆や麦をまくことができました。
名残のオクラやなすを抜き、マルチをはがし、トウモロコシの茎や草を片付け、空いたスペースのすべてに麦をまきました。白い寒冷紗をかけたところはそら豆です。麦が育ってくる来春には夏野菜や小豆など、あいだに植える予定です。果たしてちゃんと麦が育ってくれるか、見守ります。
香西
いざ道志村トレイルレースの下見へ!
今年で5回目を迎えた「道志村トレイルレース」をご存知でしょうか??
トレイルレースは登山道を駆け抜けるレースのことです。
山道ならではの上りや下りの勾配がコースであり、様々な自然の景色を味わえるのが魅力です。
道志村では総距離41.3km(10時間制限)のロングコース、20.2km(6時間制限)のハーフコースの2種類がおこなわれています。
今年5月に開催された第5回大会は約1000人の参加者が集まり、たくさんの方が厳しい山道に挑戦していました。
《参考URL》
・神奈川県・山梨東部トレイルラン連絡協議会[http://www.k-y-trail.com/doushi/]
・東洋経済オンライン[http://toyokeizai.net/articles/-/24104]
↑道志村のトレイルレースが紹介されています!
今回は、来年開催予定の第6回トレイルレースの下見に同行してきました!
私なかじまは、道坂峠〜山伏峠というの約10kmの区間を歩いてきました。
道坂峠の旧道です。
現在は塞がれています。
遺跡のようになんだか趣を感じます。
大豆収穫まであとわずか!
6月下旬の種まきから早5か月。
いよいよ大豆の収穫が迫ってきました!
その様子をご覧ください!

乾燥してきたことにより、大豆が莢の大きさよりも小さくなっています。
下の写真と見比べてみれば一目瞭然です!
それでもぱっと見た感じではまだ黄色い枝豆状態です。
ヤマネの巣箱

これは板を接着しているところです。
端材からヤマネ用の巣箱ができました。
幅10センチの小さな箱ですが、すみずみまで手がかけられていて、飾っておきたくなるようなできばえです。お世話になっている木工職人さんに教えてもらってできました。
ヤマネは冬になると体にぴったりした隙間にもぐり冬眠するそうですが、夏のあいだは巣箱も利用するそうです。来年に向けて、道志でヤマネを観察できるように巣箱をかけようとおもいます。
木桶としょうゆづくり
しょうゆ・味噌・酢・みりん・酒・・・。
昔、これら醸造調味料はみんな木桶でつくられてきました。
使い続けられる木桶には微生物が住みつき、醸造に深みが増してくると言います。
しかし、今はプラスチック製の桶やタンクで醸造することが多くなり、昔ながらの木桶仕込みの調味料が消えてきています。
「道志村でしょうゆを仕込むなら昔からの形でやりたい」という私の想いにご賛同いただき、この度木桶を譲っていただきました!
いただいたのはまだ新しい、日本酒が入っていた木桶です。
お祝い事などに鏡割りで使うものです。

ヤマガラ

ヤマガラの写真が撮れました。
道志から都留へ行く県道から小径をのぼった先のお宅です。
季刊誌を配りに訪問したこのおうちでは、ベランダでお茶をしているといつもヤマガラが来るそうです。
今日もやってきて、何回か近くまで来たあと、ひまわりの種をつまんですぐに向かいの木に戻っていきました。種をつつくコツコツという音が聞こえてきました。
今年の6月にはシジュウカラのひなが巣箱からすだったこと、ウサギのあかちゃんがいたこと、リスが原木栽培しているしいたけを食べてしまうこと、
おもしろいお話が聞けてうれしい訪問でした。
香西
鳥獣供養祭

11月10日15時から、やまゆりセンター駐車場横にある供養碑の前に猟友会のみなさんが集い、供養祭が行われました。
8日の夜に開かれた猟友会の集まりで声をかけていただき、協力隊中嶌くんと香西で参加させていただきました。
式は、都留の神主さんが執り行ってくださいました。全員が頭を下げて、鳥獣の魂を呼び、今期の猟が無事行うことができるようお祈りしました。
そのあとは「やまびこ」でご飯です。猟師のみなさんからわなの種類やつくりかた、カモシカや熊の話などいろいろお話を聞くことができました。現場で教えていただける日がたのしみです。
R413フェスティバル開催!
11月2,3日に道の駅どうしにて【R413フェスティバル】が開催されました!
R413フェスティバルは「第28回国民文化祭・やまなし2013 inどうし〜ふるさと生活文化フェスティバル〜」(11/2〜11/10)の一部としておこなわれました。
ふるさと生活文化フェスティバルは次のような3部構成となっていました。
・芸能文化の部(やまゆりセンター祭り)
絵画・写真・手芸などの展示や舞踊・伝統芸能の発表会がおこなわれました。
・生活文化の部(みなもと体験館ものづくり体験)
布草履・つる細工・花炭焼きのものづくり体験が開催されました。
・食文化の部(道の駅どうし D-1グランプリ)
道志村の新名物を投票によって決める「グルメコンテスト」が開催されました。
前置きが長くなりましたが、私たち協力隊はR413フェスティバル内でおこなわれた「D-1グランプリ」に出店し、道志村の新名物づくりに挑戦してきました!
私たち協力隊からは、道志村の景勝地をモチーフにした「的様コーヒーゼリー」と道志産の大豆や米を使用した「どうしカップケーキ」で出店しました!
カップケーキの仕込みの様子です。
小麦粉、道志産大豆でつくったきな粉と豆乳、なたね油とてんさい糖シロップだけでつくりあげるマクロビオティックなお菓子です!

D-1グランプリ出店しました!
11月2日3日に行われたD-1グランプリ(どうしのご当地グルメを決める食の祭典)にて
どうしの新名物を商品開発して出品しました。出品した商品は「的様コーヒーゼリー」です。
「的様」とは道志村の伝説の残る観光名所の1つです。
的様とは・・・
むかしむかし源頼朝が1里(約4キロ)先の櫓(やぐら)から武道錬成の為に矢を射ったと伝えられている“的”、通称『的様』が道志の湯の上流にあります。『的なでると雨が降る』と言い伝えられる伝説の場所。
肌寒い季節なので、コーヒーゼリーは売れないかなとも思いましたが、大盛況で完売!!
これからもどんどん「どうしの新商品」を開発していきたいと思います。
道志村地域おこし協力隊 井口


麦畑はじめます!〜耕耘と麦播きの巻〜
前回に引き続き、麦畑ができるまでをご紹介します!
いよいよ草も片付き、畑を耕耘するまでになりました!
今回活躍してくれた相棒がこちら!!

「BULLTRA」と書いてあるので、ブルちゃんと呼ぶことにします(笑)
小回りが利いてとても使いやすいトラクターでした!
お世話になっている方のご厚意で貸していただきました。
麦畑はじめます!〜草と格闘の巻〜
この度、タイトルのとおり麦を育てることにしました!
(ちなみに以前の千々輪さんの記事にあるように、どちらがいい麦を育てられるか勝負します!)
なぜ麦なのかといえば、麦はしょうゆづくりには欠かせない原材料だからです。
村内で育てた大豆・麦でしょうゆを仕込む夢への第一歩です!
そんなわけで大豆畑に続いて新たな畑をお借りしました!
しかし、その畑はしばらく使っていなかったそうで、草が勢力拡大していました。
夏場に何度か草刈りをされていたそうですが、やっぱり雑草は強く、すぐに繁茂してしまいます。
畑の様子です。

たじろいでしまいそうな草の量でした・・・
この草のほとんどは「ヒシバ」と言われる種類のものでした。
広がるようにしっかりと根を張る厄介な雑草です。
まずは草刈りをはじめました!
わらにお

道の駅近くのたんぼで「わらにお」を見かけました。
夕方、帰り道です。
わらにおとは、わらをきれいに積み上げたものです。
円錐形につむことで雨露を落とし冬の間腐らせずに保存することができます。地域によっていろいろな積み方があるようです。
これはすらりとして、人が立っているようでした。
香西
『道志手帖』第2号ができました!

協力隊による季刊誌『道志手帖』第2号ができました!
来週村内で配布し、11月11日(月)にはホームページにもアップします。
月夜野(つきよの)絵地図、神地(かんじ)神楽、しょうゆ搾り体験記・・・
なぜ月夜野というのか? 小学校の桜の記憶、火事があったこと。水車があったこと。
詳しくは本誌をどうぞお楽しみに。